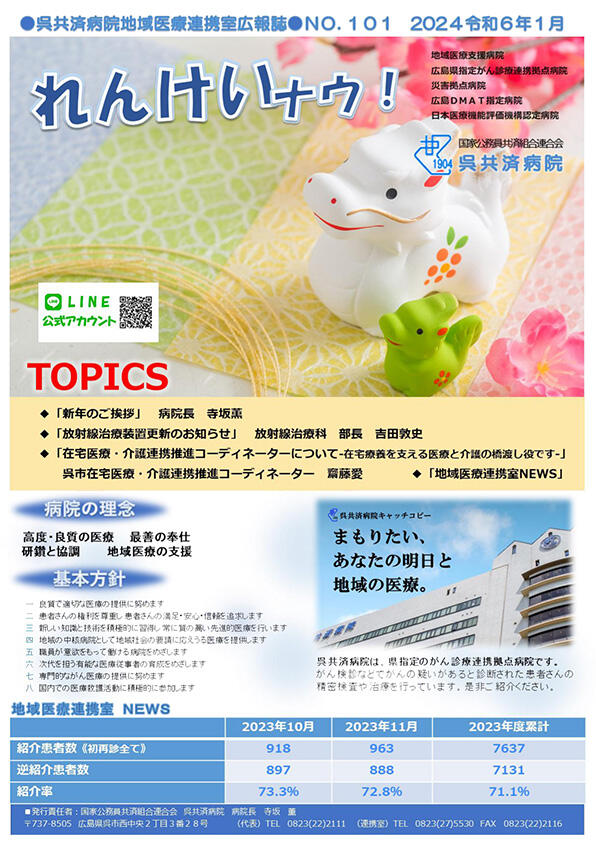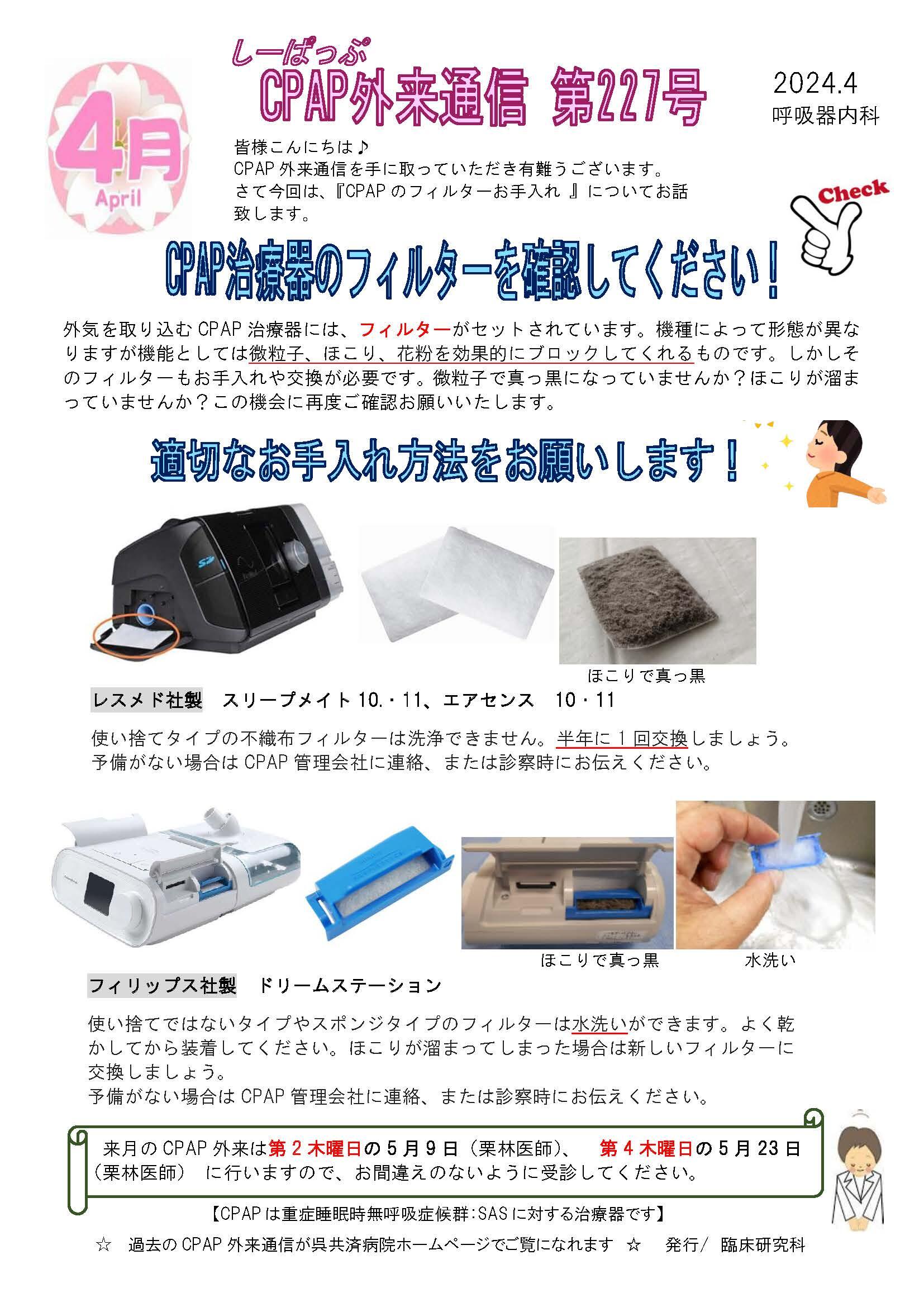外来診療 受付時間
-
初 診
8時10分~11時00分
-
再 診
8時10分~12時00分
-
予約再診
8時10分~16時00分
-
紹 介
8時20分~16時00分
休診日
土曜日、日曜日、祝祭日、振替休日、
年末年始(12月29日~1月3日)
News&Topics病院からのお知らせ
- お知らせ 人を対象とする医学系研究に関する情報公開について
- 採用情報 歯科衛生士(中途)を募集しています
- お知らせ 【健康医学センター】集団運動プログラムについて
- お知らせ ホームページアドレス(URL)変更のお知らせ
- 採用情報 事務員を募集しています
- 医療関係者 放射線治療再開のお知らせ
- 医療関係者 リニアック装置更新に伴うご協力のお願い
- 採用情報 歯科衛生士(中途)を募集しています
- 採用情報 事務員を募集しています
- 採用情報 看護師(新採用者)を募集しています
- 採用情報 臨床工学技士(新卒)を募集しています
- 採用情報 調理補助(パート午後)を募集しています
Magazine広報誌・発行物
-
主な医療認定・指定施設等

- ・保険医療機関
- ・救急告示病院
- ・労災保険指定病院
- ・生活保護指定病院
- ・難病医療指定病院
- ・災害拠点病院
- ・地域医療支援病院
- ・原子爆弾被爆者一般疾病・疾病医療機関
- ・小児慢性特定疾患医療指定病院
- ・毒ガス医療実施病院
- ・第二種感染症指定医療機関(結核)
- ・広島DMAT指定病院
- ・広島県指定がん診療連携拠点病院
- ・指定自立支援医療機関
(育成支援・更生医療・精神通院医療)
-
学生の病院実習へのご協力のお願い
当院では、次世代を担う優れた医療人育成のため、医療従事者を目指す方の実習の受け入れを行っています。
実習を通じて患者さんとの関わりを学ぶため、院内での見学、患者さんを受け持たせていただくことがありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
学生は当院スタッフの指導・監督のもとで実習を行い、スタッフ同様、厳格な守秘義務を課しておりますので、患者さんの情報が外部に漏れることはありません。
なお、協力同意は患者さんの自由意志によるものですので、協力いただけない場合でも、医療上、何ら不利益を被ることはありません。
Access交通アクセス
〒737-8505 広島県呉市西中央2丁目3番28号
-
電車でお越しの方
JR呉線・呉駅下車 徒歩約7分
-
バスでお越しの方
広島電鉄バスをご利用ください。
呉駅前より呉駅前のりば9番・10番より宝町中央循環線へ乗車、「呉共済病院前」下車 -
お車でお越しの方
立体駐車場(病院建物より道路を隔てて正面、24時間・267台収容可・有料)
陸橋にて直接病院に入ることができます。
身障者用駐車場(敷地内・救急部横)
※使用については防災センターまでお申し出ください。